
事業部が自部門のP/LだけじゃなくてB/Sも見ろって? それって、何のため?
2025年8月3日
質問
ある会社の社長が、複数ある事業部に対して、自分の事業部の損益計算書(P/L)だけではなく、事業部の貸借対照表(B/S)も責任もって見るように指示を出しました。あなたなら何と言いますか?
パターン1
それは、いわゆる事業部制をとるってことですね!
パターン2
それは、いわゆる持ち株会社制をとるってことですね!
パターン3
それは、いわゆるカンパニー制をとるってことですね!
この質問をイメージして以下のストーリーをお読みください。

|

|
活発な議論がされている経営会議
「みろくエンターテインメント」は、家電事業やコンテンツ事業、金融事業など多角的に事業を行っています。その経営会議で各事業部の部門長から報告がされています。
……ということで、今期は利益予算を達成しただけでなく、在庫の圧縮にも成功しました

家電事業部長
我々も、利益予算の達成に加えて、売掛金の圧縮に成功しました

コンテンツ事業部長
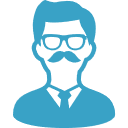
社長
みんな、ありがとう!今期は事業部長の努力のおかげで、全社の利益予算の達成だけでなく、全社のB/Sの改善も進み、借入金の圧縮もできた。この調子で来期も頑張ろうじゃないか
事業部別のP/LだけでなくB/Sも責任もってみてもらうことで、今期は全社のB/Sの改善もできたみろくエンターテインメントですが、この制度を導入するときにはちょっとした混乱もあったのです。
増収増益なのに借入が減らない、どうしてだ?
各事業部にB/Sの責任ももたせることにする1年前のことです。社長室で、社長と経理部長が話しています。
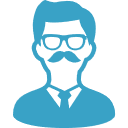
社長
事業部長のみんなの努力のおかげで今期も増収増益なのは嬉しいが、借入が一向に減らない。というより、借入が増え続けている。これはどういうことなんだ?
それは、増収増益の一方で、B/Sの在庫や売掛金の増加が止まらないためです

経理部長
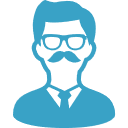
社長
なぜ、事業部長は在庫や借入を減らす努力をしてくれないんだ?
事業部長の評価はP/Lの予算達成が中心ですから。各事業部長にB/Sにも責任を持ってもらえればいいんですが……

経理部長
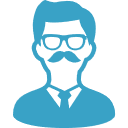
社長
なるほど。それは名案だな! P/Lを各事業部にばらしているように、B/Sも事業部別にばらせばいいじゃないか
なるほど。疑似的に各事業部をそれぞれ一つの会社に見立てるわけですね! あれっ、そういうのを何て言うんだったかな??

経理部長
質問
ある会社の社長が、複数ある事業部に対して、自分の事業部の損益計算書(P/L)だけではなく、事業部の貸借対照表(B/S)も責任もって見るように指示を出しました。あなたなら何と言いますか?
▼あなたの思うパターンをクリック▼
パターン1
それは、いわゆる事業部制をとるってことですね!
パターン2
それは、いわゆる持ち株会社制をとるってことですね!
パターン3
それは、いわゆるカンパニー制をとるってことですね!
一般的に、事業部制とは各事業部にP/Lの責任をもってもらう制度です。では、P/Lに加えてB/Sも責任をもってもらうことは何と言うのでしょうか?
一般的に、持ち株会社制とは各事業部を独立した一つの会社として、その会社の親会社が持ち株会社(ホールディングカンパニー)となることを言います。では、各事業部にP/LとB/Sの責任を負わせて、疑似的に一つの会社のように扱う制度は何と言うのでしょうか?
実は、正解はカンパニー制だったのです。では、カンパニー制で何がどう変わるのでしょうか?
それは、もしかして……
社長が各事業部にP/LだけでなくB/Sの責任も持ってもらおうと言い出したときのことです。
各事業部にP/LとB/Sの両方を持ってもらって、疑似的に一つの会社にすることを、えーっと、何て言ったかな……

経理部長
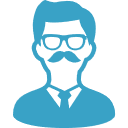
社長
俺も聞いたことある気がするぞ。事業部制ってやつじゃないか?
いや、事業部制は一般的にP/Lだけをもってもらうので、今のうちの会社が事業部制なのです

経理部長
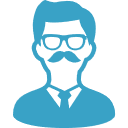
社長
わかった! 持ち株会社制じゃないか?
持ち株会社制は、本社が持ち株会社、つまりホールディングカンパニーとなって、各事業部を本当に子会社にしてしまう方法なので、違うと思います

経理部長
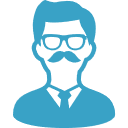
社長
じゃあ、一体なんだ??
あっ、思い出した! カンパニー制だ!!

経理部長
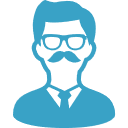
社長
カンパニーって、会社って意味のカンパニーか?
そうです。事業部に事業部ごとのB/Sももってもらうことであたかも一つの会社のようにマネジメントしてもらうのです

経理部長
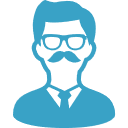
社長
なるほど。そうすれば、事業部長は売上や利益だけじゃなくて、在庫や売掛金も削減する努力をしてくれるというわけだな!
「カンパニー制」
一般的にカンパニー制とは、事業部に損益責任だけでなく、貸借対照表にも責任を持ってもらう制度です。この結果、事業部の経営判断が損益面だけに偏らず、貸借対照表も含めた経営全般を意識したものになるというメリットがあります。一方で、事業部間のシナジー効果が効きにくくなったり、事業部ごとに管理機能が必要になったりするなどのデメリットも指摘されます。なお、B/Sのうち特定の勘定科目(例えば売掛金・在庫・買掛金など)だけを事業部に配分する、いわば簡便的なカンパニー制を採用している企業もあります。
また近年は、カンパニー制を採用せずに、事業部ごとにROIC(投下資本利益率)を算出することで、事業部に投下資本を意識した経営を促すことも行われています。ROICは、事業活動に投じた資金を使ってどれだけの利益を生み出したかを示す指標です。
お知らせ
夏季休暇のため次号は8月14日掲載となりますので、引き続きご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
経営センスチェックの記事の中から、資金繰りの改善、好業績を錯覚しないためのポイントなど、テーマにそっておススメの記事を抜粋した特別版冊子を掲載しています。
最新版では、「値上げ前に考えたいコスト削減方法」について取り上げています。世界的な原油や原材料の価格高騰により、値上げが多い一方、競争戦略的に値上げをしない、または値下げに踏み切る企業もありました。
皆さまがコスト削減するにあたり、ぜひ参考にご覧ください!

X(旧Twitter)で最新情報をお届けしています
Tweets by mjs_zeikei

