
のれん償却とEBITDA ~グローバル企業における公平な業績評価指標とは?
2025年11月3日
質問
複数の国に子会社を持つ「ミロク・インターナショナル」は、各国子会社の評価を本業の業績を表す利益指標である「営業利益」を用いて行ってきました。しかし、各国子会社から、営業利益を用いた評価では、「業績を公平に評価できないのでは?」との不満の声が上がっています。各国子会社の収益力を公平に比較するには、どの利益指標を用いることが望ましいでしょうか?
パターン1
全子会社の営業利益を日本基準にあわせて再計算し、評価する。
パターン2
各国基準の当期純利益を用いて評価する。
パターン3
各国の営業利益に減価償却費やのれん償却費を足し戻した数値で評価する。
この質問をイメージして以下のストーリーをお読みください。

|
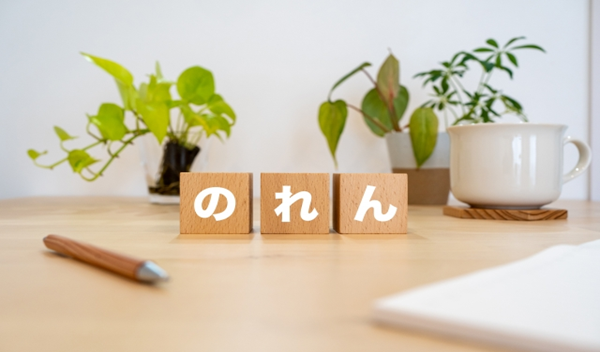
|
公平な評価のために業績評価指標をEBITDAに見直し ~のれん償却にも配慮
「ミロク・インターナショナル」は、各国子会社の業績を営業利益で評価していました。しかし、各国子会社の財務担当から、評価が公平ではないとの批判の声が数多く上がったことで、業績評価に用いる利益指標を改めることにしました。
最近、ニュースや経済記事で“のれん償却”という言葉を目にすることが増えました。実はこの“のれん償却”、グローバル企業の業績評価や経営判断にとって、とても重要なキーワードになります。ミロク・インターナショナルの業績評価では、この“のれん償却”にも配慮しました。その結果、各国子会社からの不満の声も止み、各国子会社の業績評価に対する納得性は大きく改善することとなったのです。
営業利益での業績評価に各国子会社の不満が増大
現在は営業利益を基準に各国子会社の業績評価を行っていますが、実際の業績に照らして、低い評価を受けているように感じています

A国子会社・財務担当
わたしも同様に感じています。各国で会計制度が異なるため、B国のように、減価償却費の負担が重くなるような会計制度のもとでは、営業利益が小さく評価されてしまいます

B国子会社・財務担当
A国の会計制度においてものれん償却費の負担が大きく、営業利益が小さくなってしまいます

A国子会社・財務担当
たしかに、各国の税制、会計制度、経済環境の違いによって、営業利益の数値は異なります。このままでは、各国子会社は業績評価に対する不満を抱えたままとなってしまいます

日本本社財務担当
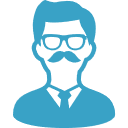
日本本社社長
わが社の成長のためには、各国子会社が同じ方向を向いて仕事に励んでくれる必要がある。各国子会社の評価に用いる指標に工夫を加える必要がありそうだ
これを受けて、ミロク・インターナショナルは、公平な業績評価を行うことができるように、評価に用いる利益指標を改めることにしたのです。
質問
複数の国に子会社を持つ「ミロク・インターナショナル」は、各国子会社の評価を本業の業績を表す利益指標である「営業利益」を用いて行ってきました。しかし、各国子会社から、営業利益を用いた評価では、「業績を公平に評価できないのでは?」との不満の声が上がっています。各国子会社の収益力を公平に比較するには、どの利益指標を用いることが望ましいでしょうか?
▼あなたの思うパターンをクリック▼
パターン1
全子会社の営業利益を日本基準にあわせて再計算し、評価する。
パターン2
各国基準の当期純利益を用いて評価する。
パターン3
各国の営業利益に減価償却費やのれん償却費を足し戻した数値で評価する。
単一基準に基づいて各子会社の比較を行うことで、各国の会計基準の違いによる差異の影響を排除することは可能です。しかし、各国の会計基準から日本基準への変換作業は負荷が大きく、現実的ではありません。そこで採用したのが、減価償却費やのれん償却費の影響を排除したEBITDA(Earnings before Interest、 Taxes、 Depreciation and Amortization、イービットディーエー)による業績評価でした。
当期純利益は、金利・税率・為替差損益など事業外の要因の影響が大きく、各国制度によってその値は大きく変化します。したがって、各国子会社の事業の収益力を評価するうえでは、不適切であるとされます。そこで採用したのが、減価償却費やのれん償却費の影響を排除したEBITDA(Earnings before Interest、 Taxes、 Depreciation and Amortization、イービットディーエー)による業績評価でした。
各国の会計基準によって、会計処理のルールが異なります。とくに、減価償却費やのれん償却費は、その金額が大きいため、異なる会計制度のもとで各国子会社の業績を公平に評価するためには、営業利益に減価償却費やのれん償却費を足し戻した利益指標であるEBITDA(Earnings before Interest、 Taxes、 Depreciation and Amortization、イービットディーエー)を用いることが適切であるとされます。
EBITDAにより、のれん償却・非償却など異なる会計処理の影響を業績評価から排除
そこで、評価に用いる指標を、国ごとの会計制度や運用ルールの違いに左右されにくい形に整えるための会議を行うことにしました。
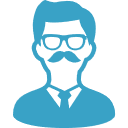
日本本社社長
各国の会計制度や運用ルールの違いによって、各国子会社の評価が変化するのは適切ではない。評価を改めることにしよう
各国の会計制度によって、単年度における減価償却費やのれん償却費の金額は大きく変化することになります。そこで、営業利益に代えて、EBITDA(注)を用いるのはどうでしょうか

日本本社財務担当
(注)EBITDA はEarnings before Interest、 Taxes、 Depreciation and Amortizationの略称で、イービットディーエーと読みます。
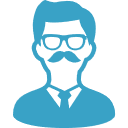
日本本社社長
EBITDAとは、どのような利益指標なんだ?
EBITDAは営業利益に減価償却費やのれん償却費を加えます。EBITDAは、営業利益に非現金支出費用を足し戻すことで、事業の稼ぐ力を捉えることのできる利益指標であるとも言われます

日本本社財務担当
現地に新工場を建設する必要がある場合、A国の会計制度では減価償却費負担が大きくなってしまいます。減価償却費の影響を排除して評価していただけると、純粋な事業の業績で評価をしてもらえるように思います

A国子会社・財務担当
のれん償却費も国や会計基準で扱いが違います。B国では毎期費用計上されますが、他国では毎期費用化されないこともあります。EBITDAであれば、このような会計処理の影響を受けることなく評価していただけるように思います

B国子会社・財務担当
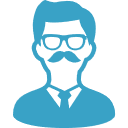
日本本社社長
よし、それでは、業績評価指標を、営業利益からEBITDAに改めることにしよう!
以上の議論を踏まえ、ミロク・インターナショナルはより公平な業績評価を行うため、営業利益からEBITDAによる評価に改めることにしました。
「EBITDA,EBITA」
グローバルに事業を展開する企業においては、国ごとに会計制度が異なります。とくに減価償却やのれん償却に関するルールは大きく異なることもあるため、各国子会社の業績を公平に評価するためには、営業利益(金融収益がある場合、営業利益に受取利息、受取配当金、持分法による投資利益を加えます)に減価償却費(Depreciation)やのれん償却費(Amortization)を足し戻した利益指標であるEBITDA(Earnings before Interest、 Taxes、 Depreciation and Amortization、イービットディーエー)を用いることが望ましいとされます。
のれん償却は、企業買収などで発生する“目に見えない価値”を会計上で分割して費用化するものです。会計上、のれんを非償却とするもの、一定期間で償却するものなど、国によって扱いが大きく異なるため、グローバル企業の業績評価では悩みのタネになりがちだからです。
なお、設備や工場などの固定資産が極めて大きい場合には、減価償却費を足し戻すことで利益が過大評価されてしまうこともあります。その場合は、営業利益にのれん償却費のみを足し戻すEBITA(Earnings before Interest、 Taxes and Amortization、イービッター)を用いることもあります。
経営センスチェックの記事の中から、資金繰りの改善、好業績を錯覚しないためのポイントなど、テーマにそっておススメの記事を抜粋した特別版冊子を掲載しています。
最新版では、「値上げ前に考えたいコスト削減方法」について取り上げています。世界的な原油や原材料の価格高騰により、値上げが多い一方、競争戦略的に値上げをしない、または値下げに踏み切る企業もありました。
皆さまがコスト削減するにあたり、ぜひ参考にご覧ください!

X(旧Twitter)で最新情報をお届けしています
Tweets by mjs_zeikei

